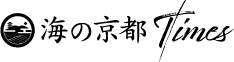京都府北部7市町の海の京都エリア。ここにはキラリと光る、ふるさと納税の返礼品がある。そんな返礼品のものづくりに迫る記事の2回目では、海の京都で生み出された「食」の名品にスポットを当てる。
キラリと光る独自商品 ~ふるさと納税返礼品のものづくりに迫る②~
まちと文化
その日本酒は淡いピンク色
その日本酒は、ロゼワインのような優雅な淡いピンク色で、味わいは果実酒のように甘ずっぱい。舟屋のまち伊根町に蔵を構える向井酒造㈱(伊根町平田)が醸す「伊根満開」。杜氏を務める向井久仁子さんが初めて商品化した銘柄だ。
話題性のある酒を

向井さんが進学した東京農業大学の醸造学科で、品種開発も手掛けていた教授からのアドバイスがきっかけだった。「精米の醸造技術が上がっており、全国にはうまい酒があふれている。これからは話題性のある酒を」
そこで、向井さんは卒業研究で濃い紫色の古代米を使った赤い酒に挑戦。卒業までに間に合わず、研究は後輩が引き継いだ。蔵に戻り、教授から赤い酒ができたとの知らせを受け、試しに飲んだところ味は良くなかったという。
「恩師に連絡したら、叱咤激励を受けました。『学んだことを生かすのは今だろう』と」。そこから蔵に閉じこもり、試験醸造を繰り返す毎日。麹、古代米、白米などの最適なバランスを探り当て、蔵に戻って1年目で新しい日本酒を完成させ発売。1999年5月のことだった。
舟屋のまちを多くの人に
向井さんは「詳細は企業秘密ですが、酒造りの常識からは外れているかもしれません」と笑う。蔵に戻った頃は今と違い、観光客はまばらだった。舟屋群で知られる港町を多くの人に知ってもらうため酒の名前には町名を付け、向井さんがお気に入りの言葉「満開」を加えた。
国内外で販売
町内で育てた古代米で造る赤い酒はすぐに新聞で報じられ、話題となった。テレビ番組などでも紹介され、その評判は町内から近隣市町、日本全国、海外にまで広がった。今では欧州や米国、オーストラリア、シンガポール、香港などで淡いピンク色の日本酒が売られている。価格は720㍉リットル瓶で税込み2200円。
向井さんは「酒造りの面白さを教えてくれた教授、社長を務める弟ら蔵のスタッフ、そして何よりお客様が伊根満開を高みに連れて行ってくれた」と目を細め、完全無農薬米を使った酒など新たな日本酒造りに意欲を燃やしている。
港町で評判のローストビーフ
日本海に面した港町の舞鶴市。かまぼこやズワイガニ、カキ、トリガイなど、名物はやはり海の幸が多いが、同市のふるさと納税返礼品の人気ナンバーワンは地元の精肉店が作るローストビーフ。舞鶴西地区のアーケード商店街に本店を構える㈱ABCフーズサービス(舞鶴市引土)の看板商品で、累計10万食の販売実績を誇る。
黒毛和牛の最高級を厳選

商品名は「A5ランク厳選和牛ローストビーフ」。同社取締役の田村寿英さんによると、使用する肉は黒毛和牛、格付けは最高級のA5ランク。そしてA5の中でも最上のBMS10~12の肉のみを使う。さらに、脂の融点が低くあっさりとしたうまみのあるオレイン酸含有量の多い肉を指定して仕入れるという徹底ぶりだ。
下味は、素材の風味を最大限に生かすため薄味に。焼き上がりを安定させるために肉は300㌘程度に切りそろえ、「絶妙な仕上がり」(同店)を追求する。付属のタレも黒毛和牛に合うあっさりとしたものを選んでいる。
ローストビーフランキングで全国1位に

田村さんは「ローストビーフが好きで休日には必ず買って研究し、試行錯誤の結果、店頭に出せるようになりました。使用部位、肉の大きさ、焼き時間、調味料など研究を重ね、自分が食べたいと思える、どこにも負けない商品へと育ちました」と自信をのぞかせる。店頭価格は90㌘入り税込み1千円。
舞鶴市のふるさと納税返礼品としてエントリーしたのは2019年。口コミでその評判が広がり翌年には、ふるさと納税サイト「ふるぽ」のローストビーフランキングで全国1位に。21年も引き続きナンバーワンを獲得している。サイト「さとふる」では黒毛和牛使用の高級ローストビーフで実質1位に。楽天サイトでも上位に付け、舞鶴市の知名度向上にも一役買っている。
舞鶴の名とともに全国へ

人気のローストビーフを全国に届けようと公式通販サイトも開設。全国の〝ファン〟の声に対応し、家庭の食卓に店の味を届けている。田村さんは「リピーターが多く、食べた方から『大切な人に贈りたい』との声も頂いており、大変ありがたいです。舞鶴の名と一緒に、さらに全国へ広がればうれしい」と話している。
軟らかな渋皮栗の甘納豆

豊富な食材で知られる京都丹波。この地域の綾部市には、地元丹波の名産を活用しようと生み出された甘納豆作りの技術がある。「軟らかさには自信があります」。こう胸を張るのは、同市栗町に本社を置く㈱中村屋の専務・中村博文さん。同社は硬くなりやすい食材でも甘納豆に加工できるのが強みで、渋皮付きの栗を軟らかで濃厚な味わいに仕上げた人気商品が「渋皮栗甘納豆」だ。
始まりは黒豆から
同社の創業者は、中村さんの父で社長の保さん。同市で生まれ育った保さんは中学校を卒業後、「菓子作りができれば、食べていくには困らないだろう」と愛知県の甘納豆業者の元へ修業に出る。古里に戻り、甘納豆を作り始めたのは1971年。滑り出しは好調だった。
ところが、78年ごろから業績はじりじりと低迷。危機感を抱いた保さんは、地元の名産に目を付けた。「丹波で甘納豆を作っているのだから、『丹波黒豆』を甘納豆にしよう」。今では当たり前のように思うが、当時は高級な黒豆を菓子に使うことすら珍しく、黒豆の甘納豆は斬新な発想だった。
ただ、これまで黒豆の甘納豆がなかったのは、価格のほかにも理由があった。一般的に甘納豆の材料は小豆や金時豆。黒豆はこれらの豆と性質が異なるため、同じように調理したのでは硬くなってしまう。甘納豆には不向きだと考えられていた。
看板商品が誕生

黒豆を買い込み、煮ては失敗の日々が2年間続いた。そんなある日、保さんの目に留まったのが、妻の春子さんが購入した圧力鍋。当時は今ほど普及しておらず珍しいもので、可能性を感じた。圧力鍋を使い始めて約2カ月、ようやく求めていた軟らかさに到達。80年、看板商品の黒豆甘納豆「丹波銘菓丹波黒」が誕生した。
次の一手へ、製法を応用
丹波黒は普通の甘納豆の数倍もの価格だったが、「黒豆」という付加価値によって贈答品などとして人気が出た。「高級甘納豆」の市場開拓により経営の危機を乗り越えた同社は、次の一手に打って出る。丹波黒の製法を応用した、栗の甘納豆だ。
丹波黒の発売から2~3年後、まずはむき栗を甘納豆にした「栗納豆」を発売した。さらにその10年後、取引先から「これも使えませんか?」と持ち込まれたのが、渋皮付きの栗。かつての黒豆のように、当時は甘納豆には使われていない食材だったという。
濃厚な和のモンブラン

「軟らかく」。その時の気温や湿度に合わせて食材と対話するように調理する技術は、渋皮付きの栗にも生かせた。でき上がった甘納豆は、あっさりとした「栗納豆」とはまた違った濃厚な味わい。保さんの技術を引き継ぐ博文さんは「栗の風味を逃さないように、ある程度の水分を持たせている」と説明する。
渋皮付きの栗を用いた甘納豆は、「渋皮栗甘納豆」として商品化した。一粒20㌘以上の大振りの実を使い、栗の甘みと渋皮のほのかな渋みが味わえるのが特長で、〝和のモンブラン〟のような甘納豆だ。15粒入りが税込み3456円、20粒入りが同4320円。