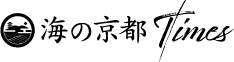酒発祥の地で今、酒蔵の多様性が花開く
まちと文化

海の京都の日本酒は、酒質が多様。全12蔵ある酒蔵ごとに、味わい、香り、舌触り、キレや余韻などが異なり、同じ地方の酒とは思えないほど。このため、兵庫灘の男酒、京都伏見の女酒、新潟の淡麗など、有名な酒処で表現されるようなエリア単位での形容は難しく、海の京都はこれまで知る人ぞ知る酒処でした。
西日本は水が軟水傾向にあるため、当地域の酒蔵も軟水で仕込むことが多い、といった共通性もあるものの、やはり酒質はバラバラ。その理由のすべてを網羅することはできませんが、海の京都の酒の魅力を紐解く上で、とても大切なポイントとして、地域の歴史と、食文化の変遷があります。

キーワードは「多様性」。その背景には、水と食の歴史、地域が急激に豊かになった時代、そして各酒蔵独自の進化がありました。
口当たりの柔らかい水に恵まれた海の京都

「半島」と呼ばれる地域は海水が混ざりやすく、良い水が出にくいと言われています。しかし、海の京都の丹後半島は、半島の割に鉄分が少なく、おいしい水が出る…例えば、宮津市の眞名井神社に湧き出る清水は遠方からも水を汲みに訪れる人があるほどの名水で、非常に柔らかく口当たりのいい水です。
海の京都では全般的に、このような柔らかい水に恵まれており、昔から、人口の割に多くの酒蔵が存在してきました。酒蔵は良い水がでる場所にできるものだからです。
海の京都は山の京都?

酒のほとんどは水ですので、酒の味わいや口当たりの大部分が水で決まるといっても過言ではありません。海の京都は酒はもちろん、農業など様々な面で水の量・質ともに恩恵を受けており、他地域が水不足の時でも当地域では水が切れないといったことも多々ありました。
その根源は、山が豊富にあること。今でこそ「海の京都」という呼称で呼ばれるようになったのですが、海だけでなく実は山も豊富にあり、山が蓄えた水がすぐ近くの町に流れ込むことで恩恵を受けてきたのです。
しかし、海の京都と一言に言っても、実は南北70km以上になる広大なエリア。その中に点在する各酒蔵で水源水脈が異なることから、やはり「蔵ごとに味わいが違う」ことにつながってきました。
とはいえ、大昔からその傾向があったわけではありません。昭和初期までは「少し甘みのある柔らかいお酒」という傾向があり、概ねどの蔵も同じ方向性だったようです。では、この地域の酒は、これまでにどういう変遷を辿ってきたのでしょうか。
海の京都は「日本の酒」発祥の地

日本酒、いわゆる「清酒」の発祥は奈良市または伊丹市と言われていますが、清酒が生まれるよりも前、日本酒の起源となる「酒」が始まったのは、海の京都の「丹後」であるという記録が残っています。
今から約600年前に書かれた丹後一の宮 元伊勢籠神社所蔵の文献に「伊勢の酒殿明神は丹後国より勧請す。和朝の酒の根本是なり」とあり、丹後は伊勢神宮に酒を伝えた起源の地であると伝えられています。故に、酒というものは丹後から始まり、そこから伊勢に伝わったことが分かります。

丹後は伊勢神宮と非常に深い関係にあり、伊勢神宮外宮に祀られている「豊受大神」はかつて、丹後地方の地主神様でした。その豊受大神が、同じく伊勢神宮内宮に祀られている天照大神(あまてらすおおみかみ)のために、日本で初めて稲作を始めたのが、丹後の「三日月田(月の輪田)」です。
今でも、地域の祭りには日本酒がつきもの。ハレの日には日本酒が飲まれる文化は今も継承されており、神様ごとと日本酒は長きに渡って、深い関係があります。
神の酒が最初に作られたのが丹後であること、また酒造りの名人とされ、万病に効くと言われていた羽衣天女の伝承があるなど、日本の酒のルーツに関わる伝承が存在するのが、この海の京都なのです。
質素な食事と酒の時代

そんな酒のルーツが息づく海の京都ですが、実は貧しい生活を送る時代が長く続きました。生活の基盤といえば、稲作を中心とした米づくりや、生魚を食べるなど質素な生活が主だったのです。そして、この地域風土は酒にも大きな影響を与えていました。
このことについて、舞鶴市にて古物商・コンサルタント業を営んでおり、当地域の酒の変遷について詳しい、ダンディ・ライオンの中西哲也氏(元ハクレイ酒造会長)にお話を伺いました。

「丹後は貧しかったので、景気が良くなるまでは質素な食事でした。だからお酒も、味が華美なものより、お魚に合うような少し甘みのある柔らかいお酒が多かったと思います。淡白で、甘みを殺さないような。お金になるいいお魚などは、都会に流れていましたから、それが地域の食に合う酒だったんだと思います」
中西氏はこの事について「ガチャマンが始まるまでは」と付け加えました。
食が急激に豊かになり、お酒も多様化

ガチャマンとは、海の京都・丹後地方における高級絹織物「丹後ちりめん」の急激な発展を指す言葉です。織を「ガチャっ」と織れば「万単位のお金」が入ってくる、といった意味です。
「昭和初期までは丹後のお酒は甘かったんですが、ガチャマンの時代を経て、どんどん多様化していきました。昔は蟹やいい魚は都会に出ていたけど、地元でも消費されるようになったのもあると思います。豊かになって、京都市内からもたくさんお客様が来られるようになり、都会の味が求められるようにもなりました。それに合わせて伏見の甘口や灘の辛口など、有名なお酒にどう近づけるか?と各蔵が勉強していったんですね。その影響もあって、甘口や辛口、いろんなお酒ができるようになっていきました。」
ガチャマン景気によって他地域から様々な文化が当地域に流れこみ、そのニーズ、お客様の多様性に1つ1つ対応していった結果、酒も多様化していった…。そして、この地域の景気の伸びは、とてつもない速度での成長であったことから、多様化の流れも「急激に」起こったのです。
近年伸びた蔵だからこその、多様性

この時代を経て、海の京都の酒は、田舎酒から都会の味に変化していきました。その後、平成4年の「級別廃止」によって、都会との味比べはさらに加速し、作り手の個性がさらに際立つようになってきた、と中西氏は語ります。
特に2000年頃からの各蔵の技術的な躍進は大きく、当地域からも金賞酒が出るようになってきました。
「酒質がバラバラなのは、近年になって伸びた蔵だから」。他地域で見られるような、代表銘柄の酒質にひっぱられるようなことがなく、各酒蔵の自己研鑽によって伸びた地域だからこそ、現代の酒質の豊富さにつながっているのです。
様々な流派が酒の個性を生み出した
食文化の豊かさと酒の味わいとの関連性の他にも、海の京都の酒蔵の多様性につながる視点があります。それは、酒造りに大きな影響を与える「杜氏(とうじ)」の存在でした。杜氏とは、酒造りの最高製造責任者。酒の味わいの方向性を決定づける監督とも言える存在です。
竹野酒造代表の行待佳平氏によると、当地域の酒蔵における杜氏の変化が、結果的に酒蔵ごとの個性になっているそうです。

「この地域の杜氏はもともと、但馬杜氏(兵庫県北部を拠点としていた杜氏)がほとんどでした。但馬杜氏のつくる酒は濃醇で、味の濃いものが多かったんです。でも宇川(京丹後市丹後町)は丹後杜氏だったし、ハクレイさんは南部杜氏を入れたこともありました。玉川(木下酒造)さんの杜氏フィリップハーパーさんも南部杜氏の技術を学んでおられます。うちは以前は但馬でしたが、今杜氏をしている息子は能登で修行しているんです。これだけいろんな杜氏がいるんだから、一概にこの地域の酒の特徴って何、とひと括りに言えるのかな?と思うところはありますね。」
エリアの特徴以上に、各蔵の個性へ
行待氏は続けて「地域、という意味での特徴が無くなってきた一方で、みんながあがいているのが、独自の特徴をつくっていくということですね。みんな必死だと思います。」と語ります。
海の京都の酒蔵に限らず、現在の消費者の味の好みに合わせ、いわゆる売れるお酒として味を「合わせていく」ということは、全国的に行われてきました。しかしその結果、どこの酒も似たような味わいになってしまい、個性が失われてきたという事実もあります。
日本は全国の米がどこにでも流通する国です。このことからも味が平均化され、どの町でも似たような味わいの酒が飲まれるようになった。それは酒だけでなく、食生活全般で言えることでしょう。

平均化されてきた時代から、多様性の時代へシフトする現代。もともとから多様性の歴史を歩んできた海の京都は、エリアという括りにとどまらない「各蔵、各地域の個性」という方向性へ歩んでいるのかもしれません。
「大概は、人の縁ですね。物事がどんどん変わっていくのは。杜氏にもネットワークがありますので、どの蔵もそれぞれの人的ネットワークで技術を蓄積していっていると思います。それを、もっともっと出していく方向ですね。」
地域の食と共にある、変わらない本質。

中西氏、行待氏、当地域の酒造りに深く関わってきた二人の言葉に共通していたのは、「各蔵の工夫と切磋琢磨によって、進化してきた」ということでした。
各蔵にフォーカスすればするほど、その背景にはやはり地域文化との深いつながりがあります。近年、蟹やブリなどの高級食材が多く食べられるようになれば、それに合うお酒を。昔ながらの食事にも、合うお酒を。お酒と食文化は切り離せないもの。いくら多様化が進んでも、地域の食との関係性は、今も変わらず残っています。
また当地域の酒蔵は湧き水の恩恵を受けている蔵がほとんどで、土地ごとの水が酒を構成しています。近年では地元の米を使って酒を醸す動きもどんどん進んでおり、酒造りの始まりと終わりは、酒米をつくる農家さんと共に迎えます。
蔵ごとに異なる、その土地の水、その土地の米でできた酒を、その土地でとれた食とともに味わう醍醐味。グローバル化が進んできた現代の行き着く先は、とてもローカルな、土地ごとの唯一性でした。そこに酒蔵の技術の蓄積、切磋琢磨が加わり、その場でしか味わえない体験につながるのでしょう。
中西氏はこう語ります。「これからが楽しみです。もう一度地元をリサーチしなおして、地元の食文化を見直すチャンスですね。そして、丹後の料理には辛口が合うという蔵も、甘口が合うという蔵もあっていい。料理に合う、という同じ答えに辿り着くはずです。」

食やお酒が多様化しても、地域の食と共にあるという本質は変わらない。
好みのお酒を探すだけでなく、地域風土を感じながら、食に合わせて愉しむ。そんな、感性の幅を広げる飲み方こそ、これからの酒の楽しみ方かもしれません。